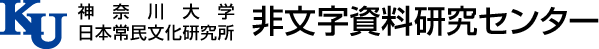| 掲載日・放送日 | 媒体名 | タイトル | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024年9月15日 | 琉球新報 | 大龍柱は正面向き | 9月13日に那覇で開催されたシンポジウム「首里城と沖縄神社」の報告記事。「参加したパネリストは、首里城正面の一対の大龍柱の向きについて、正面向きで一致。このままでは、互いに向き合う相対型になる可能性が高いとして、県民に更に正面説を訴えていくことが必要と結論付けた」。 |
| 2024年9月12日 | 毎日新聞 | れきし箱:首里城「大龍柱」論争の深層=伊藤和史 | 2019年に焼失した首里城再建について、大龍柱の向きに関する論争を紹介した記事。記事は「「相対向き」は皇民化政策の所産で、琉球王国の象徴とされる首里城にとっては全くの異物となる。大龍柱の問題は沖縄の思想と文化、アイデンティティーの問題であることが分かる。」と結ばれている。 |
| 2024年8月30日 | 中外日報 | 神社に利用された首里城 | センターから出版された『首里城と沖縄神社―資料に見る近代の変遷』の紹介記事。 |
| 2024年8月10日 | 読売新聞 | 戦意高揚 市民の率直な反応 国策紙芝居の感想録 感動や不満伝える貴重な史料 | 紙芝居班の調査によって香川県坂出市の鎌田共済会郷土博物館で発見された「感想録」に関する記事。現時点での調査研究の進展状況を伝えるとともに、神奈川大学学生有志によるプロジェクトとして当該資料を読み解き、戦後80年を向かえる来年にはその成果を展示等で発表する予定であることを伝えている。 |
| 2024年8月5日 | 読売新聞 | 国策紙芝居 感激も苦言も 神奈川大調査 市民の感想録 香川で発見 | 紙芝居班の調査によって香川県坂出市の鎌田共済会郷土博物館で発見された「感想録」に関する記事。発見の経緯や内容について詳しく伝えている。10日の記事につづく。 |
| 2024年6月7日 | 中外日報 | 西南戦争の慰霊碑 調査報告書を刊行 | 坂井久能客員研究員により、横浜市にある伊勢山皇大神宮に立つ西南戦争の戦没者招魂碑(「明治十年西征陣亡軍人之碑」)や慰霊碑などを調査した報告書が刊行されたことを伝える記事。報告書には碑の形状、寸法、銘文のほか、刻まれた131人の出身地と名前などを収録している。 |
| 2024年5月12日 | 毎日新聞 | 「海外神社」のいま 戦後史を宿す「神国」の跡=稲宮康人(写真家) | 海外神社を撮り続けてきた自らの取り組みについて紹介している。「「神国」の跡地には、過去のみならず、撮った跡地がたどってきた戦後という時も写っている。その風景の来歴を言葉でも明らかにできればと、資料を掘り進めている。自分もまた、熱にあてられた一人かもしれない。」 |
| 2024年1月22日 | 東京新聞 | 川崎市平和館 戦時下の国策紙芝居展示 平和考えるきっかけに | 開催中のミニ企画展「国策紙芝居展~戦争へいざなう言葉と物語」を紹介する記事。センターから国策紙芝居を多数提供して協力した。国策紙芝居の実演もあり。 |
| 2024年1月21日 | 読売新聞 | 戦意発揚狙った紙芝居 川崎で企画展 「情報読み解く大切さ」=神奈川 | 開催中のミニ企画展「国策紙芝居展~戦争へいざなう言葉と物語」を紹介する記事。センターから国策紙芝居を多数提供して協力した。国策紙芝居の実演もあり。 |
| 2023年12月2日 | 神奈川新聞 | 教訓に建築史の視点で向き合う 神奈川大特別助教・姜明采さん |
姜明采研究員にインタビューした記事。東京都慰霊堂を研究テーマとした経緯や復興記念館の展示リニューアルに取り組んだことなど、今後の展望も踏まえて説明されている。神奈川大みなとみらいキャンパスで開催中のパネル展と二日間にわたって実施されるシンポジウムについても紹介されている。 |
| 2023年8月17日 | 読売新聞 | 関東大震災100年 「知識の宝庫」帝国大図書館炎上 萱原白洞「東部大震災過眼録」 | 人的被害だけではなく図書館や書店や古書店にも甚大な被害があったことを伝える内容。その末尾に「作品で見る」というコーナーがあり萱原白洞「東部大震災過眼録」を紹介している。非文字では21世紀COEプログラムの時代に萱原白洞「東部大震災過眼録」に関する展示とシンポジウムを開催した経緯もあり、今回協力することとなった。 |
| 2023年6月10日 | 読売新聞 | 撃沈米艦 衝撃物語る 特攻兵器「桜花」攻撃 沖縄の海底で発見=神奈川 | 特攻兵器「桜花」によって撃沈された米駆逐艦マナート・L・エベールが沖縄本島から北に約140キロの海底で見つかったことを伝える記事。坂井久能客員研究員がコメントを寄せている。 |
| 2022年7月27日 | 琉球新報 | 首里城大龍柱 向きの検証(下) 根拠図は別目的 向き情報無く不変示す | 後田多敦研究員により、大龍柱を相対向きとするグループが根拠とする「寸法記」は根拠にならない(「寸法記」を誤読している)ことを詳細に分析した内容。 |
| 2022年7月26日 | 琉球新報 | 首里城大龍柱 向きの検証(上) 絵図は実態映さず | 後田多敦研究員により、大龍柱を相対向きとするグループが根拠とする「寸法記」は根拠にならない(「寸法記」を誤読している)ことを詳細に分析した内容。 |
| 2021年7月11日 | 琉球新報(新報小中学生新聞2021.01.27) | つなぐ平和④ 国策紙芝居 子供の遊び 戦争に染まる | 小中学生にもわかりやすいようにまとめられた国策紙芝居に関する記事 |
| 2021年7月11日 | 沖縄タイムス つなぐ平和 | 変わる子供文化4 紙芝居や遊び 戦争一色に | 小中学生にもわかりやすいようにまとめられた国策紙芝居に関する記事 |
| 2021年7月4日 | 神戸新聞・週刊まなびー | 紙芝居 戦争協力の内容に 子供の遊び 戦時色に | 小中学生にもわかりやすいようにまとめられた国策紙芝居に関する記事 |
| 2021年1月28日 | 沖縄タイムス | ギルマール写真と首里城正殿(下) 伊藤家正殿写真も撮影か 大龍柱の「原型」とらえる | 沖縄県設置から3年が過ぎた1882(明治15)年6月に、イギリスから沖縄を訪れたフランシス・ヘンリー・ヒル・ギルマールが滞在中に撮影した沖縄の写真に関する後田多敦研究員による考察記事。 |
| 2021年1月27日 | 沖縄タイムス | ギルマール写真と首里城正殿(上) 置県後の首里城など撮影 図版とセットで残る | 沖縄県設置から3年が過ぎた1882(明治15)年6月に、イギリスから沖縄を訪れたフランシス・ヘンリー・ヒル・ギルマールが滞在中に撮影した沖縄の写真に関する後田多敦研究員による考察記事。 |
| 2020年11月29日 | 西日本新聞 | 石峰山中に射撃場跡? 旧制若松中 軍事教練に使用 神奈川大学名誉教授 田上さんが確認 | 若松区小石の石峰山中で、旧制若松中学(現在の若松高)の射撃訓練場跡地とみられる構造物が見つかったことを伝える記事。元研究員の田上繫氏や元研究協力者の若宮幸一氏により確認された。 |
| 2020年11月25日 | 沖縄タイムス | 王府側と会見 撮影も許可 1877年の首里城訪問 フランス人が見た琉球(上) | 熊谷謙介研究員による、フランス海軍中尉ジュール・ルヴェルトガの紀行文全文の読解記事。 |
| 2020年11月23日 | 琉球新報 | 大龍柱巡り議論白熱 首里城討論会 来場者130人、関心高く | 11月22日に開催された公開討論会の様子を伝える記事。国の「首里城復元に向けた技術検討委員会」は「寸法記」を根拠に大龍柱の相対向きを主張してきたが、1877年にルヴェルトガが撮影した正殿の写真により正面向きの大龍柱が確認されたことにより論争なとなっている。オンライン参加した後田多敦研究員は「相対設が整理するためには、1877年までの間に王府が大龍柱の向きを変えたという証拠を探さないといけない」と指摘。 |
| 2020年7月2日 | 南日本新聞 | 薩摩行列鮮やか 不明の絵巻原本発見(1面)、使節行列政治の場 琉球「礼の国」を演出、町人 にぎわい楽しむ(11面) | 1面記事では、『日本近世生活絵引;琉球人行列と江戸編』の編纂作業中に、これまで失われ所在不明になっていた絵巻の巻一の原本が発見されたことを伝えるとともに、現存する写本と対比して、原本の意義を説明。 11面記事では、『日本近世生活絵引;琉球人行列と江戸編』の刊行を伝え、渡辺美季先生と丹羽謙治先生へのインタビューから、『絵引』の見どころを解説。 |
| 2019年9月13日 | 読売新聞 | 「共感力」引き出す 紙芝居 集中促す効果 内外で注目 | 現在、紙芝居の魅力が教育現場で見直されていることを紹介する内容が中心。その中で、紙芝居には過去の負の歴史もあることの解説として非文字センターの活動を紹介。 |
| 2019年8月23日 | 中外日報 | 大日本帝国と共に姿消す 海外神社200社の跡地写真紹介 | 文化面 展示会期中に実施したメディア向け展示解説時のインタビューに基づく実施報告記事。 |
| 2019年8月15日・22日合併号 | 仏教タイムス | 戦前海外神社の跡地 写真展『帝国日本』の残影 大日本帝国の信仰面の統治を考える | 展示会期中に実施したメディア向け展示解説時のインタビューに基づく実施報告記事。 |
| 2019年8月15日 | 毎日小学生新聞 | おもちゃも戦場へ 戦争中の紙芝居 子どもたちに宣伝 | 1面と2面に掲載。『オモチャの出征』『チョコレートと兵隊』『子馬とはがき』の画像を掲載。安田常雄氏(センター客員研究員)へのインターヴューに基づく分かりやすい記事となっている。 |
| 2019年8月2日 | 神奈川新聞 | 帝国の残影感じて 海外神社の跡地写真で紹介 4日まで横浜 | 写真展開催の案内。インターヴューに基づき詳しく展示内容が紹介された記事。 |
| 2019年7月31日 | 毎日新聞 | 海外神社 帝国の影追う 14の国・地域200ヵ所 写真に | 東京夕刊 7頁社会面(全992字)。写真展開催の案内。インターヴューに基づき詳しく展示内容が紹介された記事。 |
| 2019年7月29日 | 朝日新聞 | 戦地の神社跡写真@横浜 | Around Tokyo欄において、写真展開催の案内。 |
| 2019年7月26日 | 週刊金曜日 | 写真展|「帝国日本」の残影 海外神社跡地写真展 | 1242号 情報欄 写真展開催の案内。 |
| 2019年7月14日 | 毎日新聞(西部朝刊) | 北九州・惣牟田集落:中世の耕地景観、復元を 官兵衛ゆかりの墓石で裏付け 地元出身研究者が本格調査 | 文化面<日曜カルチャー>(全1,866字) 田上繁氏(本学名誉教授・センター客員研究員)へのインタビューと、現場取材に基づき、歴史的背景についても詳しい内容の記事となっている。 |
| 2019年5月1日 | しんぶん赤旗 | 国民主権の意味あいまいに | 中島三千男氏(本学名誉教授・センター客員研究員)へのインタビューをもとに、一連の「代替わり」に関してまとめられている。「焦点・論点」 天皇「代替わり儀式」の問題点/識者に聞く/宗教学者・上智大学特任教授島薗進氏と共に掲載。 |
| 2019年4月29日 | 東京新聞 | 代替わり考 憲法との兼ね合い腐心 政府新設「退位の礼」 | 「退位礼正殿の儀」に関する記事において、中島三千男(本学名誉教授・センター客員研究員)のコメントを掲載。 |
| 2019年4月5日 | 東京新聞 | <視点 沖縄から>「琉球処分」140年 「遠い記憶」ではない | 1879年(明治12年)の「琉球処分」を契機に多数の亡命者が出たことや「琉球救国運動」について説明。そこから、140年を経た現代の沖縄が置かれた現状に関する問題提起を行っている。 |
| 2018年10月 | 子どもの文化 2018年10月号(子どもの文化研究所) | 『国策紙芝居からみる日本の戦争』を読む 239作品の解説と6編の論考 3年間の研究成果が460頁のテキストに(片岡輝 氏:子どもの文化研究所所長) | 片岡輝氏による概要紹介。内容要約を含めて7ページにわたって読み解かれている。特に論考編の要約は論点が整理されており、当該書籍を読むための予備知識として有益である。 |
| 2018年9月28日 | 日本経済新聞 | 紙芝居が担った戦時宣伝――生々しい戦闘描写や動物の物語、戦意高揚の仕掛けに、安田常雄(文化) | 研究班代表の安田常雄先生(神奈川大学特任教授)のインターヴュー記事。当センターにおいて241点の紙芝居を所蔵するに至る経緯。戦時下での制作や上演の実態、そして戦後とともに多くが失われたことなど。これまでの研究成果と今後の課題についてまとめられている。 |
| 2018年9月12日 | 南日本新聞 | 「薩藩勝景百図」研究報告書を刊行 神奈川大、HPも公開 | 『日本近世生活絵引 南九州編』が刊行されたこと。神奈川大学学術機関リポジトリから公開されたことなどが記事となった。 |
| 2018年8月20日 | 「けんせつ」(東京土建一般労働組合)第2255号 | 紙芝居からみる戦時 街頭は統制、国策一色に | http://www.tokyo-doken.or.jp/news/news2018/2255/2255-08.pdf (accessed 2018-10-01) |
| 2018年7月26日 | 信濃毎日新聞 | 上演担い総力戦体制支えた地域の人々民衆の意識解明手掛かりに | 全体の紹介とともに、共著者である信州大学人文学部の大串潤児教授の分析も多く紹介。「県内での上演の詳しい実態は分かっておらず、新聞記事や役場文書の分析などが必要としている。」として、長野県の実態に引き寄せて記事をまとめている。 |
| 2018年7月9日(夕刊) | 毎日新聞(評者:栗原俊雄) | Topics:戦意高揚に利用されたメディア 国策紙芝居 241点を研究 神奈川大のグループが本刊行 |
『国策紙芝居からみる日本の戦争』刊行紹介。第1編の解題編からは「爪文字」を取り上げている。また、第2編の論考編の多彩なテーマにつていも簡潔に紹介。第3編の全国調査(暫定版)」についても触れられている。 |
| 2018年6月30日 | 図書新聞(評者:早川タダノリ(編集者)) | 戦時期紙芝居の全容に迫る―きわめてミニマムなメディアであった紙芝居が、戦意高揚と総動員体制建設の使命を帯びて人々の生活に入りこんでいった実像を解き明かした、貴重な研究成果 | 近年、アカデミズムでの戦時紙芝屈研究が前進してきた中で本書が刊行された意義を大きく評価するとともに、紙面の許す範囲で内容について論評している。 |
| 2018年6月8日 | 読書人(評者:野上暁(編集者・子ども文化評論家)) | ヴィジュアルプロパガンダとしての紙芝居 取材を交えて克明に検証 戦時下の子ども文化研究にとっても貴重 |
週刊読書人 ウェブ https://dokushojin.com/article.html?i=3440 本書につてい、「戦時下のメディア検証はもちろん、子ども文化研究にとっても貴重であり、ここから読み取れることが多々ある。」として、子ども文化研究の視点から紹介。 (accessed 2018-10-01) |
| 2018年6月2日 | 朝日新聞(評者:横尾忠則(美術家)) | (書評)『国策紙芝居からみる日本の戦争』安田常雄〈編著〉 | 美術家である横尾忠則氏による書評。幼少期の実体験から語り始め、紙芝居が現在の自らの絵画の原郷だろうかと回想している。 |
| 2018年6月号 | 東京人 | ||
| 2018年5月15日~5月31日 | 日本経済新聞 | ポスターでたどる明治十選 | センター第5共同研究班所属の青梅市立美術館学芸員の田島奈都子氏による連載。毎回、1枚のポスターを取り上げ、その見どころや時代背景、商品にまつわる多彩な話題が盛りだくさんな内容。 2018/05/15(1)千葉商店「シルヴァーライト」 2018/05/17(2)岩谷商会 2018/05/18(3)日本郵船 2018/05/21(4)大阪硫曹株式会社 2018/05/22(5)森永西洋菓子製造所 2018/05/24(6)サッポロビール 2018/05/25(7)三越呉服店「東京勧業博覧会」 2018/05/28(8)高島屋呉服店 2018/05/29(9)中山太陽堂「クラブおしろい」 2018/05/31(10)神戸湊川貿易製産品共進会 |
| 2018年5月14日 | 南日本新聞 1面、21面 | 国宝島津家文書の「薩藩勝景百図」よみがえる江戸期の姿 | 神奈川大学非文字資料研究センターにおいて共同研究がなされていることの紹介記事。 |
| 2018年4月29日 | 読売新聞(評・加藤徹(中国文化学者 明治大教授)) | 「国策紙芝居からみる日本の戦争」 日本人の深層映す | 「紙芝居は、あなどれない。本書は、日本人の深層を考えるヒントの宝庫でもある。」と、紹介している。 |
| 2018年4月8日 | 西日本新聞 | 「黒田二十四騎」の1人 竹森次貞 子孫の墓が若松に惣牟田集落 守り継ぐ 神奈川大学名誉教授ら調査 | 田上繁名誉教授(非文字センター第7班)の調査に関する記事 |
| 2018年3月31日 | しんぶん赤旗 | 天皇「代替わり」儀式 | 2019年に行われる天皇の「代替わり」に関連する儀式について、中島三千男名誉教授(非文字センター第6班)のコメント掲載。 |
| 2017年12月2日 | 東京新聞 | 戦前回帰見え隠れ 大がかりな行事は明治からの「伝統」 | 中島三千男名誉教授(非文字センター第6班)のコメント掲載。 |
| 2017年11月3日 | 八重山毎日新聞 | 得能壽美氏 第33回八重山毎日文化賞を受賞 | 共同研究第/第4班「日本近世生活絵引-行列から見る都市生活空間-」 に所属の得能壽美(とくのう・としみ)氏が第33回八重山毎日文化賞を 受賞しました。 ■八重山毎日新聞 http://www.y-mainichi.co.jp/news/32499/(アクセス:2017.11.6) |
| 2017年9月19日 ・10月20日 |
角川文化振興財団(2017年10月12日選考)/徳川記念財団(平成29年9月14日選考) | 上原兼善氏 角川源義賞と徳川賞をダブル受賞 | 共同研究第/第4班「日本近世生活絵引-行列から見る都市生活空間 -」に所属の上原兼善氏が、その著書『近世琉球貿易史の研究』により、 角川源義賞と徳川賞をダブル受賞しました。 ■第39回角川源義賞 http://www.kadokawa-zaidan.or.jp/news/2017/10/000398.php(アクセス:2017.11.6) ■第15回「徳川賞」 http://www.tokugawa.ne.jp/encourage_2017.htm(アクセス:2017.11.6) |
| 2017年5月1日 | 岩波書店『世界』5月号第八九五号 | 神国と帝国 神社からみるアジアと日本の戦後 稲宮康人 公募作品156 | 非文字資料研究センター研究協力者の稲宮康人氏(写真家)による写真掲載。汕頭神社跡、太原神社跡、南京神社跡、佳冬神社跡、新城社跡、松江神社跡、泉神社跡、靖国神社。 |
| 2017年3月21日 | BSジャパン | 空から日本を見てみよう+【福岡県若松~飯塚】 | 非文字資料研究センターが提供した資料が一部利用された。 |
| 2016年12月24日 | 日経プラスワン 3ページ | スリッパ、実は日本で生まれた――土足厳禁、外国人向けに、草履の感覚、庶民にも定着(たどってなるほど) | 内田青蔵センター長のコメント掲載。 |
| 2016年08月17日 | 日本経済新聞 夕刊 | 「国策紙芝居」、敵を鬼や虫に、戦時中、米英首脳を描く、世論への影響を研究、神奈川大。 | 安田常雄教授、原田広研究協力者のコメントならびに写真掲載。 |
| 2015年12月5日 | サンデー毎日 | 大学プレスセンターニュースダイジェストVol.91 思わぬ掘り出し物に触れる大学には「お宝」がいっぱい |
「戦意高揚紙芝居コレクション」241点の所蔵に関する紹介記事 |
| 2015年11月15日 | 北日本新聞 | 連載 紙芝居が描いた戦争 1~10 | |
| 2015年10月22日 ~12月22日 |
徳島新聞 | 連載 紙芝居が描いた戦争 1~10 | |
| 2015年9月 | GRAPHICATION 200号」(富士ゼロックス(株)広報誌) | 非文字文化とは何か | 非文字文化の魅力という特集が組まれ、元非文字資料研究センター研究員、橘川俊忠先生へのロングインタビュー記事が掲載。 |
| 2015年8月21日 | 中外日報 | 資料と写真から海外神社に迫る | 刊行物『海外神社とは?-史料と写真が語るもの』の記事が掲載されました。 |
| 2015年8月15日 ~10月31日 |
十勝毎日新聞 | 連載 紙芝居が描いた戦争 1~10 | |
| 2015年8月4日 ~10月6日 |
陸奥新報 | 連載 紙芝居が描いた戦争 1~10 | |
| 2015年7月21日 ~2015年10月6日 |
高知新聞 | 連載 紙芝居が描いた戦争 1~10 | 7.21「フクちゃんで国威発揚」安田常雄、7.28「アジア解放の「大義」説く」森山優、8.4「華々しく勇ましい「皇軍」」、8.11「暮らしの全てを動員」原田広、8.18「国への「御奉公」万能標語に」原田広、8.25「悲痛な最期 庶民に伝える」原田広、9.1「市民生活の模範示す」大串潤児、9.8「機密保護 国民に自覚促す」森山優、9.29「母性が強調された社会」大串潤児、10.6「描かれない「敵」の姿」安田常雄 |
| 2015年7月18日 ~ |
北羽新報 | 連載 紙芝居が描いた戦争 1~10 | |
| 2015年7月11日 ~ |
長野日報 | 連載 紙芝居が描いた戦争 1~10 | |
| 2015年5月14日 | 毎日新聞 大阪夕刊 2頁 総合面 | 次世代の戦後:記憶と表現 海外神社 写真家・稲宮康人さん | 海外神社の跡地を撮影する旅を続けている非文字資料研究センター研究協力者の稲宮康人氏(写真家)に関する記事。 |
| 2014年10月18日 | 南海日日新聞 | 「琉球嶌真景」も掲載 | 非文字資料研究センターから刊行された『日本近世生活絵引(奄美・沖縄編)』に関する記事。 |
| 2013年11月30日 | 朝日新聞 朝刊 神奈川全県・2地方 | (アート)戦争宣伝担った紙芝居 神奈川大センター購入・展示 /神奈川県 | 非文字資料研究センターが「国策紙芝居」241組を購入。12月4日公開研究会と展示のお知らせ。 |
| 2013年8月14日 | 西日本新聞 | 複眼68回目の夏 海外神社のいま 破壊、放置、再建…日本との関係映す | 中島三千男教授による記事。海外神社研究全般に関する内容。 |
| 2013年8月7日 | 神奈川新聞 | 「あの戦争」を知る-2 苦い記憶と複雑な現在 海外神社の跡地 | 中島三千男教授に対するインタヴュー記事。海外神社研究全般に関する内容。 |
| 2010年12月28日 | 朝日新聞 夕刊 2社会 | 災害復興・支援を考えるシンポジウム 来月8~10日、兵庫・西宮で【大阪】 | 非文字資料研究センター研究員・北原糸子先生の「絵巻物と児童画で見る震災」と題する講演と作品の展示について。 |
| 2010年10月27日 | 読売新聞 東京朝刊 文化 |
絵巻で見る関東大震災 | 関東大震災直後の模様を克明に描いた絵巻「東都大震災過眼録(とうとだいしんさいかげんろく)」。神奈川大学での特別展で公開中。 |
| 2010年10月22日 | 毎日新聞 地方版/神奈川 | 関東大震災:「生き地獄」子どもが被災絵 きょうから神奈川大で惨状記録展 /神奈川 | 関東大震災(1923年9月)の惨状を記録した絵画展「関東大震災を描く」開催について。 |
| 2010年8月21日 | 毎日新聞 東京夕刊 社会面 | 絵巻:関東大震災、直後の庶民 炊き出し・法要…復興描く--東京で24日から初公開 | 関東大震災の被災者の様子を描いた日本画家、萱原黄丘(かやはらこうきゅう)(1896~1951年)の絵巻が東京都墨田区の都復興記念館で初公開される。非文字資料研究センターの研究チームが収蔵庫の整理中に見つけたもの。 |
| 2009年7月17日 | 毎日新聞 地方版/東京 | 関東大震災:都慰霊堂の資料、神奈川大がデータベース化 /東京 | 関東大震災の供養施設「都慰霊堂」(墨田区横網町)に保管されていた膨大な資料のデータベース化の取り組みと、非文字資料研究センターの北原糸子主任研究員のコメント。 |
| 2009年3月15日 | 毎日新聞 地方版/神奈川 | 関東大震災:震災後の東京・横浜、復興テーマに発表 町内会急増など報告 /神奈川 | 関東大震災後の横浜・東京をテーマにした公開研究会「震災復興と文化変容」。大学教授ら約100人が参加。 |
| 2008年12月3日 | 朝日新聞 夕刊 2社会 | 図面が語る海外神社 戦前建設、技師宅から20枚 【大阪】 | 発見された図面に関する中島三千男教授(日本近現代思想史)のコメント。 |
| 2007年11月10日 | 毎日新聞 地方版/神奈川 | 実験展示:歩き方の変遷探る 江戸の旅人絵や昭和初期映画も--神大で /神奈川 | 実験展示「あるく」の紹介記事。歴史民俗資料学研究科の中村ひろ子教授のコメント。 |
| 2006年11月11日 | 読売新聞 東京朝刊 福島2 |
神奈川大と連携、只見町でネットエコ博物館=福島 | 只見町と神奈川大とが連携して構築した「インターネットエコ博物館」の試験運用開始について。国指定重要有形民俗文化財指定の8000点もの町の民具や町の自然環境をインターネット上で公開する試み。 |
| 2006年1月8日 | 読売新聞 東京朝刊 福島 | 只見の豊富な民俗資料や自然景観…丸ごとネット博物館に 町と神奈川大=福島 | 只見町と神奈川大学が「仮想博物館」事業を共同で展開することに関する記事。佐野賢治教授(民俗学)のコメントなど。 |
| 2003年7月29日 | 朝日新聞 朝刊 神奈川1 | 非文字資料、体系化し世界へ COE決定の神奈川大 /神奈川 | 文部科学省の「21世紀COEプログラム」に神奈川大学が採択。 |